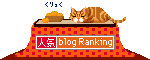QとPは、来る日も来る日も研究に没頭した。
研究室に週2回は泊まり込み、女子力とは皆無の生活を送っていた。
(しかし、言わずもがな2人とも美少女なので、ポテンシャルというのはすごいものだ。)
PはQの様子を見ながら、素材や部品を用意してくれる。
まさに阿吽の呼吸が2人の間には流れる。
まるで、数学の問題でよく見る点Pと点Qのように、連動して動いてるようだった。
Qは、Pとの研究に居心地の良さを感じていた。
この状態がいつまでも続くなら、Qは永遠に研究できそうな気さえしていた…。
そしてQは初めて抱く感情を手にする。
「もしPがいなくなったらどうしようか?」
「私は今までのように研究できるのだろうか?」
Qはそんなことを考える自分に、真っ青になる。
ずっと一人でやってきたQ。
子供から大人になるのでさえ、一人でなったと思っているぐらいだ。
「だって両親は、何もしてくれなかった」
幼少期を除き、Qはすぐに世間に注目され、お金も稼いできた。
今でも両親より遥かに稼いでいる。
そして両親は、Qをお金としか見ていない。
これは、今までの両親を見ていればわかることだ。
だから両親がいなくなっても、Qはおそらく涙も出ない。
つまり、何かを失うかもしれない…そういう恐怖をQは味わってこなかった。
悲しみや嫌悪感などは、青で表現できた。
辛い体験も青や黒で表現できた。
「この失う怖さは何色なんだろう…?」
Qは色で表せない感情に戸惑っていた。
その間にもPはQに眩しい黄色い笑顔を向ける。
QはPに聞いてみることにした。
「ねえ、恐怖って何色か知ってる?」
Pは一瞬驚き、そしてまた笑顔で答える。
「恐怖に色はないんですよ、Qさん」
「恐怖は恐怖なんです。怖いという感情は、何かを失う時以外訪れません。」
「昔の特攻隊は非難されても、なぜドローンの自爆攻撃は容認されるか…それはドローンに恐怖という感情がないからです。」
Qは黙って話を聞いていた。
「だからこそ、無=恐怖なんだと、私は思ってます。」
Pは笑顔であるが、とても真面目に話す。
そしてその目には、過去の悲しみや憂いを含んでいた。
QはPに対し、淡い透き通ったブルーな気持ちになった。
そして
「ごめんね」
と一言呟くと、Pは全てを察した顔で
「私の方こそ、すみません!Qさんじゃなかったら答えてません。」
と言った。
Qは同時に、自分がようやく人らしい感情を持てた気がした。
そして
「ねえ、P。いつもありがとう。」
そういうと、Pは
「こちらこそ」
と満面の笑みで、涙を浮かべていた。
Qはもうすぐ完成する、新AANの名前をこの時決めた。
そして明日、ようやく新AANは明日完成を迎える。
それはPも同じ気持ちだろう。